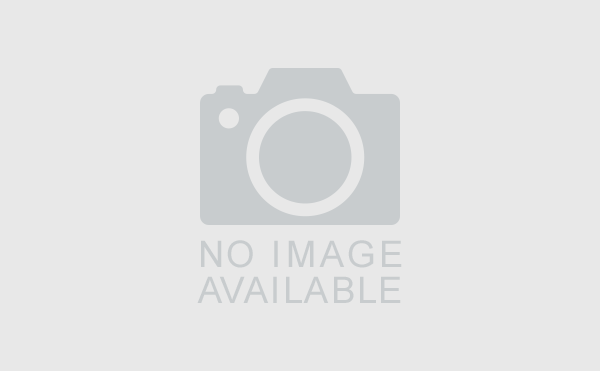7 平均をねらう必要はない
①元日「なのに」映画を観に行った
②元日「だから」映画を観に行った
現実に起きたのは、
元日に映画を観に行った。
というだけのことなのに、私たちは①だの②だのといって、それに意味をつけたがる。
そうして、他人から①と言われれば、それを悪いことみたいに受け取って、来年からはやめようと思ったりする。
②と言われれば、むしろ積極的に行うべきものとして、翌年以降もそんな行動を続けるかも知れない。
ここで大切なのは、どちらが正しいか、ということではない。
畢竟、自分がやりたいと思って、行動に移したことであれば、世の中からどう見えようといいのだ。
問題は世の中から「こう見えるから」と言って、行動を変えてしまうことなのだろう。
今年限りで、年賀状じまいすることにした。
これは世の中的な流れに乗っかったということも否めないけれども、「やりたいこと」ではなく、「やらなければならないこと」であったからに他ならない。
これまでの自分には、「やめる」という選択肢はなかった。
それが平均的日本人の在り方であり、そこから逸脱することは恐怖ですらあったのだ。
自分がどうしたい、というのはさておき、「年賀状を出す自分」が「年賀状を出さない自分」よりもよく見えていたからにすぎない。
心境の変化と言ってしまえばそれまでだが、「やめる」を選択できたことで世界が広がった感じがする。
そうして、一歩を踏み出してしまえば、そこに自分が想像していたような大きな意味はなかったということに気付く。
意味を与えなければ、現実はすごくシンプルだ。
こうして私たちは、意味を与えることによって、現実を誇大に体験してきたのだろう。
今年80歳になる父は、80歳以上になると、積極的に外に出て活動するようなことはしなくなるのだ、などと言う。
運動機能が低下し、認知症の危険性も高まるというのが主な理由であるようだが、これも数字に不必要な意味を付けている一つの例だろう。
80歳の人に平均的にそれが起こる可能性が高いからといって、自分もそうである必要はない。
平均をねらう必要はないのである。
ここで指針とするべきは、80歳の人がどうしているか、ではなく、自分がどうしたいか、だけである。
その先に、ありきたりではない未来があるような気がする。
2023.1.8 交野左絵