5 人の死を悼むということ
安倍元首相の国葬に関する論争がやまない。
英国のエリザベス女王の逝去によって、その意義がさらに問われはじめ、葬儀の本来の意味を逸脱して、賛成派と反対派による水掛け論の様相を呈してきているのには、少々閉口する。
葬儀とは本来、人の死を悼んで行うものではなかったか。
まず思うのは、国葬に値する人物であるならば、当の本人は国葬など望まないはずだ、ということだ。
そのことだけを取ってみても、生きている人間の事情で執り行われようとしているように思われてならない。
また、そんなお金があるのならば、困っている人や、未来のある人に分配するのが政治の役目だとも言える。
政治は生きている人のためにあるべきで、この場合は死者よりも優先してしかるべきなのではないだろうか。
そういう意味においても、政治と国葬は結びつけて考える種類のものではない。
法的根拠もない中、議論を経ることなく見切り発車してしまった結果がこのありさまである。
(日本における一般的な)葬儀の在りかたそのものには昔から疑問を持っていた。
この儀式には、死者および遺族の面目を保つという側面があって、それが式の大きさに影響を与えるのだ。
名士と言われるような人の葬儀は都合、盛大かつ多くの弔問客が訪れることになる。
葬儀における設えなどにも松竹梅あって、そういうものだ、と言われてもどこか釈然としないのは私だけに限ったことではないだろう。
個人的なところでいくと、母が早くに亡くなって、父が喪主をつとめて葬式を出したことがあった。
親類縁者に声をかけたり、喪服を用意したり、会場や僧侶を手配したり、することが盛りだくさんではあったけれど、それらは悲しみの延長上にあるものではなくて、淡々と事務的にこなす種類のものだった。
人の死には、日常からその人がすっぽり抜けてしまうのとは全く別の次元の大変さがあるのだ、ということを実感する経験であった。
葬儀の席で泣くことはなかった。
母の死は、他の誰の死とも違って一番身近なものであり、また壮絶な闘病の末だったということもあって、決して平静でいられるものではなかったが、舞台をしつらえられて、悲しみをせかされて、泣くというのは少し違う感じがしていた。
本当に悲しかったのは、布団に入って母を思い出す時であったり、ふとしたときに母の不在を実感する時などで、きわめて個人的なことなのだった。
でもそれらは、葬儀の席で形式的に悼むのとは違って、間違いなく心が伴っていたはずである。
「人の死を悼む」というのは実際とても個人的なもので、強制されるものでもなければ、面目を施すためのものでもないのだろう。
葬儀の在りかた自体は、コロナ禍を経て大きく変わってきているようではある。
かつてのように親類縁者がこぞって参列するイベント的な趣きは徐々に薄れ、近親者のみで執り行う家族葬というのがここ数年のトレンドとなりつつある。
これは故人の付き合いの範囲や深さによっても変わってくるので、一概には言えないが、絶対にこうしなければならないという呪縛からは多少なりとも解放されてきているようには思う。
慣習を重んじる面々からすると、こうした簡略化とも言える変化は、不届きだということになるのかもしれない。
でもこの慣習というものに縛られすぎると、人間は頑なになり、進歩は覚束ない。
この時代ならではの、また、多様性の一つの現れとして、葬儀というものを捉えなおしてみてもいい時期に来ているのかもしれない。
葬儀はあくまで残された人間の整理のために行うものだ。
死というものが永遠の別れのように位置づけられる今の時代においては、慣習に則って正しく営まれることが無難ではある。
だが私たちの目がもっと開かれて、死の捉え方自体が変われば、堅苦しい儀式など必要としなくなることもあるだろう。
100人いれば100通りのやり方があってよい。
あるいは心の中で想うだけでも、「人の死を悼む」という点においては十分かもしれない。
大切なのは、そこに弔意があるかどうかどうかだ。
そうであるならば、もとより形にこだわる必要などないのだろう。
2022.9.18 交野左絵
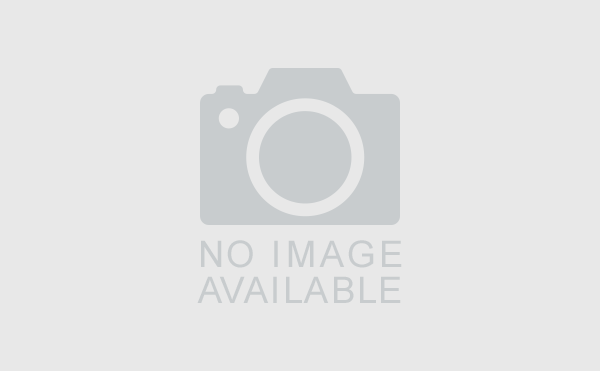
Superb blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There
are so many choices out there that I'm totally overwhelmed ..
Any suggestions? Many thanks!
自分の思いを吐き出したいだけならば、無料のもので十分です。
真剣に書き、いい考えを広めたいならば、有料できちんとしたものを作成するのをお勧めします。
パラマハンサ・ヨガナンダ著『あるヨギの自叙伝』
文章をうまく書くための本ではないですが、これを先入観なしに一冊読み切った暁には、面白いブログが書けるのではと思います。
ありがとう。
Belo post, compartilhei com meus amigos.
どうもありがとう。あなたに幸運が訪れますように。